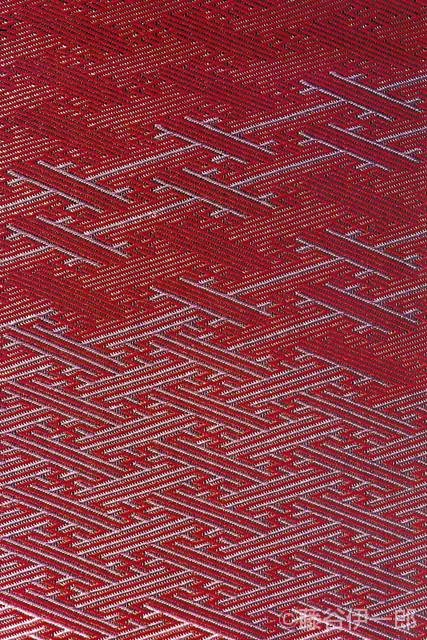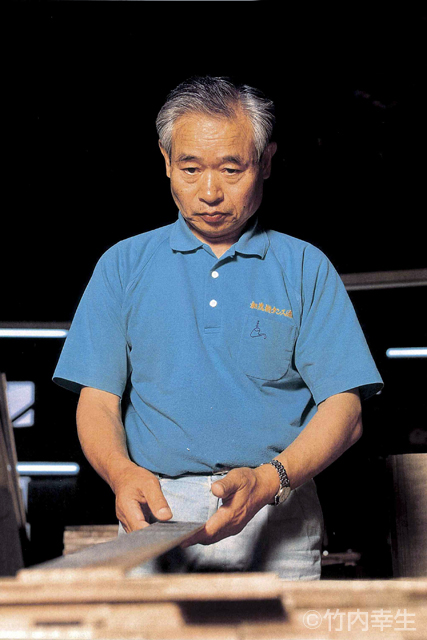白山麓の人々の心を紡ぐ伝統の手織り・牛首紬

霊峰白山を源に金沢平野へ注ぐ手取川。その手取川に沿って、白山市の鶴来地区から白山方面へ向かうと、25kmほどで白峰の集落に出ます。 ここは、かつて白山麓十八力村と呼ばれる天領でした。その後、1889(明治22)年に村制を施行、白峰村となりました。雪の多い北陸でも有数の豪雪地帯で、冬ともなれば、集落全体がすっぽりと雪に覆われてしまいます。古くから養蚕が盛んで、かつての十八力村の一つ牛首村で織られていた「牛首紬」は、今でもこの地域の特産品となっています。 牛首紬の起源は定かではありません。1159年の平治の乱で敗れた源氏(平家という説もあります)の落人が、この地に逃れ、その妻女が機織りの技に優れていて、村の女たちにその技術を伝えたのが始まりとも言われます。それが正しければ、860年以上の歴史を持つことになり、牛首紬の繊細な技術は、こうした都人の匂いなのかもしれません。 記録の上では、京都の旅籠屋松江重頼が書いた『毛吹草』(1645年)に出てくる牛頸布の名が最初です。その後、江戸後期の『白山草木士心』(1822年・畔田伴存作)には、「牛ケ首は民家二百三十軒あり繁盛の地なり、蚕を家ごとに養うて、糸を出すことおびただし」と、記されています。 最盛期、年間1万2568反も生産したと記される1934(昭和9)年頃は、総数200戸余りの機場と2社の大機業場がありました。しかし、なぜか第2次世界大戦前には、そのほとんどが姿を消しています。更に戦後、復興を試みた者のうち、残ったのは加藤機業場のみとなってしまいました。 後継者もなく、伝統の牛首紬も消えゆくかと思われました。が、「祖先の遺産は守らねば」と、1965(昭和40)年、土木建築会社・西山産業が織物部門を設け、西山家の七人兄弟から三、五、六男が紬屋に転身しました。三男西山鉄三さんの話では、当初は牛首紬の産業化など愚かなこと、と笑われたといいます。 確かに織物部門は、しばらく赤字を続け、西山産業のお荷物になっていたそうです。更に1974(昭和49)年、手取川ダムが出来、紬の里が水没しました。そのため西山産業は、白峰村日峰と鶴来町に工場を移転。紬の技術を持っていた人たちも集団で移転し、牛首紬は白峰と鶴来で再出発しました。 そんな中で、加藤機業場でも息子が跡を継ぐ決意を固めます。1979(昭和54)年には、牛首紬生産協同組合を結成。その