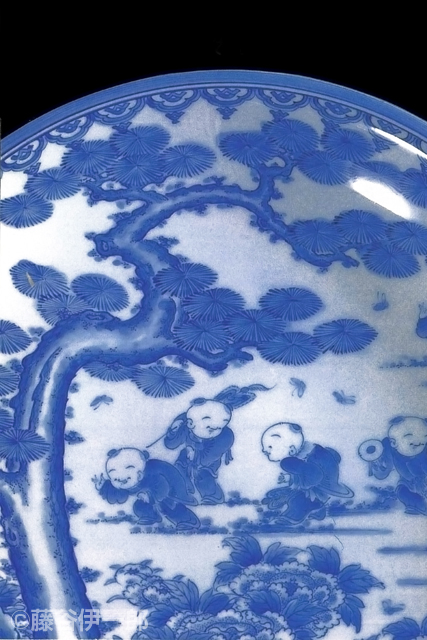武州のだるまさんは男前

暮れから正月、そして3月末頃まで、全国的にだるま市が集中します。冬はだるまの製造元にとって、文字通り暮れも正月もない最も忙しい時期です。埼玉県南東部に位置し、江戸時代には日光街道の宿駅として栄えた越谷市も、だるまの産地として知られています。 越谷だるまは、別名「武州だるま」とも呼ばれ、関東地方を中心に広く北海道から九州まで出荷されています。生産量としては、群馬県の高崎だるまに次いで全国2位を占めておリ、寅さんで有名な柴又帝釈天や同じ東武線沿線の西新井大師、神奈川県の川崎大師などの参道で売られています。 越谷のだるま作リは、口碑によれば、江戸中期、「だる吉」という人形師によって始められたと伝えられています。その後、幕末の頃、高橋八太郎という人が、本格的にだるまの製造を始め、武州だるま発展の基礎を築きました。この武州だるまの特徴は、他の産地に比べ、色が白く、鼻がやや高く、上品で優しい顔立ちをしていることにあると言われています。そのため、粋を好んだ江戸町民から「武州だるまは男前」との評判を取り、隆盛を誇りました。 だるまは、生地の作リ方から見て、昔ながらの張り子だるまと真空成型だるまとに大別出来ます。張リ子だるまは、いちょうの木で作った木型に下張り紙を貼リ、その上の和紙を貼って2~3日天日で乾かし、その後、型抜きして、膠で切リ目を貼ります。一方、真空成型というのは、どろどろに溶かした紙と鋳型を使うもので、機械化され、生地作リ専門の業者によリ、それぞれの産地に卸されています。 現在では、ほとんどの産地が、真空成型の生地を利用しておリ、伝統的な張リ子だるまは消えつつあります。そして、真空成型方式によって、量産出来るようにはなりましたが、その一方で、形が画一化され、生産者の持つ個性と味わいが失われてしまっているのも事実です。 その中にあって、武州だるまはわずかではありますが、昔ながらの張り子だるまの伝統を守っておリ、1984(昭和59)年には、だるま産地としては全国で初めて、県の伝統的手工芸品の指定を受けています。 現在、この伝統的な張り子だるまの製造元は越谷市を中心に4軒残っていますが、どの家も代々家業を継承している家ばかりです。これは、他の職人仕事と同じで熟練するまでにはそれなりの年月がかかるためでしょう。そして、各家がそれぞれ独自の木型を持ち、個性溢れるだるまを作っていま...