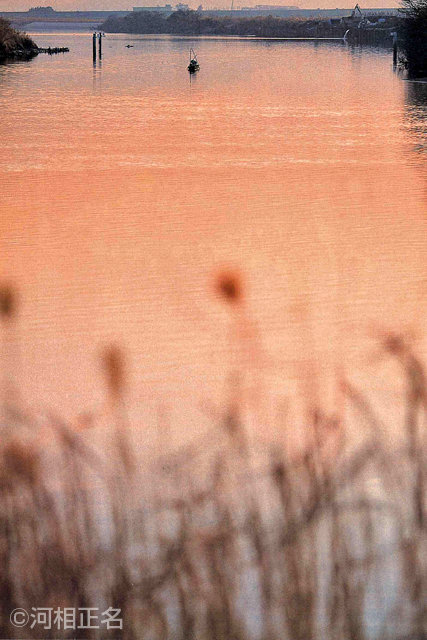ガーリック・キャピタルを標榜する青森県最南端のニンニク村

田子町は青森県最南端、南を岩手県、西を秋田県と接する県境の町。町の特産「田子ニンニク」は、知る人ぞ知る上質のニンニクで、一流レストランが指名買いするほどのブランドを確立しています。 田子でニンニク栽培が始まったのは1962(昭和37)年。隣の福地村で、小規模ながら栽培されていたニンニクの種子を、町の農協青年部が買い入れ、栽培したのが始まりです。 「福地ホワイト六片種」と呼ばれる、この種子は、その名の通り真白で、実の一片一片が、普通の品種の2倍以上もあります。更に質も非常にいいのですが、いかんせん大規模に栽培されていたわけではなく、当時はほとんど知られていませんでした。 しかし、田子で試験栽培を始めてみると、この辺りの土壌や気候が、ニンニク栽培に適していることが分かりました。田子は、十和田火山の噴火によるシラス状の土地で、水はけがいい土地です。また、冷害の原因となるヤマセも、ニンニクの敵ではありませんでした。逆に、収穫期に日照が少なく、実が大きく育つというメリットさえもたらしました。 こうして田子では、69年から「第1次5力年計画」を立て、本格的なニンニク生産を開始。その年のニンニク生産額は300万円でした。が、75年には100倍の3億円、87年には7億円と増え続け、日本一のニンニク産地となりました。 現在、ニンニク栽培は県内の他市町村にも広がり、生産量1位の座は譲ったものの、町を挙げて築いたニンニク文化で「ニンニクの首都」を標榜。町の中央には「ガーリックセンター」が建てられ、一般財団法人田子町にんにく国際交流協会が発足、世界一のニンニクの町アメリカ・カリフォルニア州ギルロイ市との姉妹提携など、ニンニクを柱にしたユニークな町づくりが行われています。