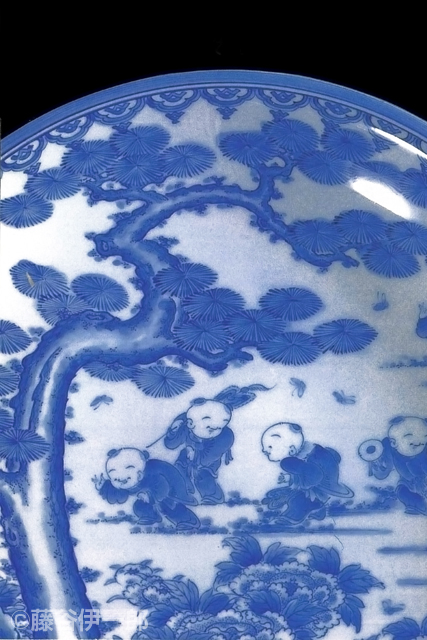取材で泊まった大村の町を散歩してみた

昨年暮れの記事で書いた大村( 長崎を開港したキリシタン大名の本拠地 )と、東彼杵( 海の見える千綿駅とそのぎ茶で有名な町 )を取材した際、大村の長崎インターナショナルホテルに泊まりました。ここは、長崎県の玄関口・長崎空港から近く、JR大村駅にも歩いて行ける場所にありました。また、主な取材地の玖島城や武家屋敷街からも近かったので、このホテルを選びました。 食事は、検索した限りでは、あまりそそられるものがなく、珍しくホテル内の和食処「桜華」でとったのですが、それでも駅の近くなら何かあるかもと、チェックイン後、ホテルから駅に向かってぶらぶら散歩してみました。ホテルのそばには、国道34号が走っていて、この国道を渡った側が、駅方面になっています。 で、国道に出た所にマックがありますが、これは論外。更にマックの裏に「有楽街」という路地があったので、好奇心が刺激され通ってみました。ただ、ほとんどスナック系で、一つあった居酒屋も、表に「横浜風」のお好み焼きともんじゃ焼きが目立つように書かれていたので、やはりこれも敬遠。こうして「有楽街」を通り抜けたら、また国道に出てしまいました。 少し行った所に駅方面へ向かう大きな通りがあり、そこを入ってみましたが、飲食店は登場せず、国道から200mほど歩いた所でお店屋さんらしいたたずまいを発見。「お菓子のナガサキヤ」でした・・・。Googleのローカルガイドによる口コミは4.4でかなり高評価ですが、ケーキ屋さんで夕食はないっすな。 その先も飲食店はなさそうなので、少し先でUターンをして、道路の反対側を歩いてみました。すると、国道まであと70〜80mという所に、スカートをなびかせたマリリン・モンローと、トレンチコートに手をつっこんだハンフリー・ボガートがいました。二人は、ロニースコッツという店のウィンドウの中におり、この店名とモンローに惹かれて、ふらふらっと店に入りかけた私。でも、どうやらダイニングバーっぽいので、ドアの前で踏みとどまり、ホテルに戻って食事をすることにしました。 ちなみに、ロニースコッツというのは、ロンドンにある伝説的なジャズ・クラブで、店名はオーナーのロニー・スコットにちなみます。彼もミュージシャンで、店では生演奏が行われ、ソニー・ロリンズなども出演したことがあるそうです。 またジミ・ヘンドリックスが最後に演奏したクラブとしても知...